感染管理情報
次亜塩素酸ナトリウムへの曝露
- Q 透析室で感染性胃腸炎対策の環境整備を行う際に、バケツ(蓋なし)で水3リットル+ミルトン60ml(200ppm)準備し、準備後すぐに環境整備しました。(環境整備に回る際も蓋なしでした。所要時間準備~環境整備まで約30分程度でした)環境整備が終わり、残った液を廃棄しようとした際に「次亜塩素酸ナトリウムは蒸気ならびに吸入毒素があるから蓋を開けたままのやり方は危険だからやめた方がいい。体の害になる」といわれました。
(1)次亜塩素酸ナトリウム希釈水200ppmではたして蒸気毒素・吸入毒素による人体への害が発生するのか
(2)また希釈水でどのくらいの濃度から蒸気毒素・吸入毒素による人体への害があるのか
この2点についてご教示頂ければ幸いです。 - A
次亜塩素酸ナトリウムは不安定な化合物であり、その溶液は、常温においても緩やかに低濃度の塩素ガスを発生しながら分解します。分解する速度は日光(特に紫外線)への曝露、温度、溶液中の重金属や塩類の存在、pHにより影響を受けます1)。
次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用する際に、空気中に塩素臭を感じる場合、空気中の塩素濃度は0.2~3.5ppm(1~10 mg/㎥)程度であると言われています2)。
では、どのくらいの濃度の塩素に曝露すると人体に影響が出るのでしょうか。塩素をはじめとする人体に有害な物質に人が曝露した場合、影響が発現する空気中濃度の域値を示した「急性曝露ガイドラインレベル(Acute Exposure Guideline Level, AEGL)」というものがあります。曝露のレベルは、AEGL-1からAEGL-3までの3段階に分かれています。AEGL-1は曝露した人が著明な不快や刺激を感じるが、曝露を中断すれば影響を一過性に止めることが可能なレベル、AEGL-2は、不可逆的かつ長期的な健康被害を受ける可能性が出現するレベル、AEGL-3は生命に影響を及ぼすことが予想されるレベルと定義されています3)。
アメリカ合衆国環境保護庁(Environmental Protection Agency, EPA)は、0.5ppmの塩素に10分間曝露するとAEGL-1レベルの健康被害が、2.8ppmの塩素に10分間曝露するとAEGL-2レベルの健康被害が生じると規定しています4)(表1)。
また、化学物質が人の健康や環境に与える影響について国際的な評価を行っているICSC(国際化学物質安全性カード)プロジェクトは、10%未満の濃度の次亜塩素酸ナトリウムへの短期的曝露により眼、皮膚、気道への刺激症状が生じ、長期または反復曝露を受けると皮膚感作が起こるとしています。さらに曝露予防策として、取り扱いの際には換気を十分に行い、手袋を着用し、眼の保護を行うよう勧めています5)。
以上から、空気中への塩素の揮発による吸入毒性や、溶液がこぼれることによる眼や皮膚への曝露を防ぐために、次亜塩素酸ナトリウム溶液は短時間であっても蓋つきの容器に保管することが望ましいと考えられます。
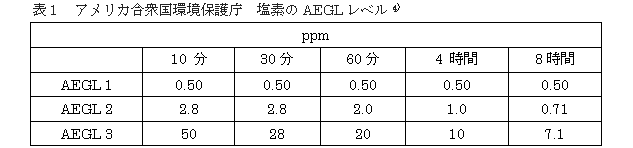
- 日本ソーダ工業会. 安全な次亜塩素酸ソーダの取扱い 平成18年11月20日改訂
http://www.jsia.gr.jp/data/handling_03.pdf (確認日2013年1月29日) - Health Protection Agency(英国保健保護局). Sodium hypochlorite Incident management
http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1194947394890 (確認日2013年1月29日) - Environmental Protection Agency(アメリカ合衆国環境保護庁). Acute Exposure Guideline Levels (AEGLs)
http://www.epa.gov/opptintr/aegl/pubs/define.htm (確認日2013年1月29日) - Environmental Protection Agency(アメリカ合衆国環境保護庁). Chlorine Results
http://www.epa.gov/opptintr/aegl/pubs/results56.htm (確認日2013年1月29日) - 国立医薬品食品衛生研究所 国際化学物質安全性カード 次亜塩素酸ナトリウム(溶液、活性塩素< 10%)
http://www.nihs.go.jp/ICSC/icssj-c/icss0482c.html (確認日2013年1月29日)
この質問にご回答いただいたのは

坂本史衣先生
学校法人 聖路加国際大学 聖路加国際病院 QIセンター
1991年聖路加看護大学卒業、聖路加国際病院公衆衛生看護部を経て、1997年米国コロンビア大学公衆衛生大学院卒業。聖路加国際病院看護部勤務の後、日本看護協会看護研修学校 感染管理認定看護師教育課程専任教員。2002年より現職。米国感染管理疫学資格認定機構 (CBIC)による感染制御認定資格(CIC)取得。日本環境感染学会理事、日本医療機能評価機構患者安全推進協議会感染管理部会副部会長。