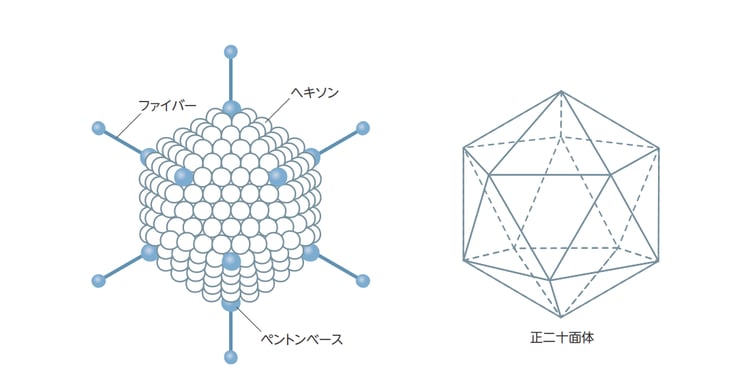感染管理情報
新紙幣北里柴三郎先生と感染管理・社会への影響|学習ブログ|ASP Japan合同会社

新しいお札の顔
2024年7月から、北里柴三郎博士の肖像画が新たに千円札に採用されます。
この変更を通じて、博士の業績が広く知られることになり、医療従事者のみならず、一般の人々にとっても「医学とは何か」を再考する良い機会になるでしょう。

細菌学研究の道
北里柴三郎博士の業績は、特に伝染病に関する細菌学研究への貢献が顕著です。
1894年、香港で黒死病(ペスト)が発生した際、博士は青山胤通と共に日本からの調査団として派遣され、世界に先駆けてペスト菌を発見しました。
博士の科学者としてのキャリアは、若いころオランダ人軍医マンスフェルトと出会ったことで医学を志したことから始まりました。
その後、ドイツに留学し、「細菌学の始祖」とされるロバート・コッホに師事しました。
さらに、ノーベル生理学・医学賞を受賞するエミール・ベーリングなどの著名な研究者とも切磋琢磨しました。
この留学期間中には、破傷風菌の純粋培養に成功するという画期的な成果を達成し、細菌学における深い知識と緻密な研究技術を習得しました。
帰国後の逆境と研究拠点建設への支援
博士は、未解決な病気が多かった当時の日本で、ドイツでの成果を活かすため、世界各地からの招聘を断って1892年に帰国しました。
しかし、上司であった緒方正規との「脚気菌」発見に関する議論から生じた当時の医学界との対立があり、理想的な研究環境を得ることができませんでした。
そのような状況の中、北里博士の非凡な才能を惜しんだ長与専斎たちの支援により、日本での研究を開始することができました。
初の研究拠点となった「伝染病研究所」の建設に最も大きく協力したのが福沢諭吉です。福沢諭吉はその後も、日本初の結核専門病院「土筆ヶ岡養生園」の設立や、医療事業の継続的な支援を惜しみませんでした。
この縁は、のちに北里博士が慶應義塾大学医学部創設に関わるきっかけになりました。
免疫血清療法と北里研究所の創設
北里博士は、コッホのもとで取り組んでいた結核の治療法の研究を続けました。
また、日本でも流行したコレラについて、「免疫血清療法」を行って成果をあげ、ジフテリア血清に関しては伝染病研究所に入院した多くの人々を救っています。
こうした血清療法の開発は、世界中の感染症治療に革命をもたらしました。
北里博士は、ジフテリア、破傷風、腸チフス、コレラ、ペスト、赤痢などの免疫血清の製造事業を推進し、技術的な支援も惜しみなく提供しました。
彼の長年にわたる努力の成果は、国民の生命と健康を守るために使われました。
しかし、研究所は内務省にあるべきとする北里博士の意に反して、1914年「伝染病研究所」が文部省に移管されると、博士は同研究所を辞しました。
その後、実践的な伝染病の治療と予防を志す研究者たちとともに、「北里研究所」を新たに設立しました。
医療分野へ数々の貢献
「医の基本は病気の治療と予防にある」という信念のもと、北里博士は病原体の発見だけでなく、治療法や予防法の確立に向けた一貫した研究を行いました。
この姿勢はワクチン接種や感染予防措置の重要性を広め、公衆衛生の認識を高めることになります。
また、北里博士は福沢諭吉への恩義を感じ、慶應義塾大学医学部の初代部長を無報酬で務めました。
彼は第一次世界大戦の影響で不足してしまった体温計の国内生産を目指し、他の医師らと協力して体温計製造会社(現テルモ株式会社)を設立しました。
その他、看護師養成所の新設、予防医学教室、食養研究所など、医療分野における数々の先駆的な試みも推進しました。
さらに、日本医師会の初代会長として、医師や看護師が患者ケアをより効果的に行えるよう、健康保険制度や医薬分業の確立にも取り組みました。
現代医学における北里柴三郎の遺産
北里博士は医学研究を通じて、文豪であり医師の森鷗外をはじめとする同時代の多くの著名人と交流しました。
科学的立場を尊重する北里博士は、多くの逆境に直面しながらも、病気から民衆を救うための研究と治療に専念し続けました。
北里博士の卓越した研究能力と治療法の確立への不屈の精神は、彼の同僚や後進の研究者に大きな影響を与えました。
例えば、北里博士を支えた北島多一はジフテリア以外の病気に対する血清療法の応用研究を行い、赤痢菌を発見した志賀潔や、サルバルサンを開発した秦佐八郎、黄熱病の研究をした野口英世など、多くの研究者が医学と人道に貢献しました。
このように、北里博士の遺産は、科学的成果だけでなく、学問的対話がもたらした現代医学研究や社会への影響にも見ることができ、今日においてもその価値は計り知れません。

2024年5月(令和6年)
坪田 康佑(つぼた こうすけ)
看護師、看護・介護ジャーナリスト。
ETIC社会起業塾を経て、無医地区への医療提供体制づくりに取り組む。2019年に診療所や訪問看護ステーションなど全事業承継。現在は訪問看護師向け雑誌などでの連載や高齢者向け新規事業開発に取り組む。開発に関わった三角巾はグッドデザイン賞を受賞する。